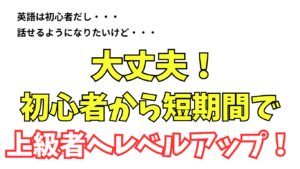会社員から「マイクロ法人」「フリーランス」へ!お金を無駄しない準備について完全解説

なぜ今、会社員からフリーランスを目指す人が増えているのか?
時代背景:働き方の価値観が大きく変化している
近年、日本では「働き方改革」が大きな社会的テーマとなり、多くの企業が労働環境の見直しに取り組んでいます。
残業の削減、有給休暇の取得推奨、リモートワークの普及などが進む中で、個人が「どう働くか」を自ら選ぶ流れが加速しています。
特に2020年以降のパンデミックをきっかけに、オフィスに縛られない働き方が急速に浸透しました。
この変化によって、会社員という働き方が「唯一の安定」ではなくなり、時間や場所に縛られずに働けるフリーランスという選択肢が現実味を帯びてきました。
また、企業側も即戦力となる外部人材を積極的に活用する方向にシフトしており、フリーランスの需要は年々高まっています。
こうした背景が、会社員からフリーランスへの転身を後押ししているのです。
データで見る!フリーランス人口の推移と将来予測
内閣府の調査や独立系シンクタンクの報告によると、2023年時点で日本国内のフリーランス人口は約1,770万人にのぼり、労働人口の約25%を占めています。
これは10年前に比べておよそ1.5倍の増加です。
また、副業・兼業を含めた柔軟な働き方をする人も含めると、その数は今後も増え続けると予測されています。
特に20代〜30代の若年層を中心に、「自己実現」や「自由なライフスタイル」を理由にフリーランスを選ぶ人が増加傾向にあります。
一方で、40代以上のミドル層も「セカンドキャリア」「会社に依存しない働き方」を意識し始めており、幅広い年代で関心が高まっています。
こうした数値的な裏付けからも、今後フリーランスという働き方は一時的なトレンドではなく、労働構造の一部として定着していくことが分かります。
副業解禁と生成AIの登場がもたらす追い風
2018年に政府が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を公表して以降、大企業を中心に副業を容認する企業が増えています。
かつては「副業禁止」が当たり前だった時代から一転、現在では副業を推奨する企業も出てきています。
これは会社員にとって、会社に依存せず、収入の柱を複数持つという発想を後押しするきっかけとなっています。
さらに、2023年以降のChatGPTなどに代表される「生成AI」の登場により、個人でもスピーディかつ高品質な成果物を生み出すことが可能となりつつあります。
これにより、デザイン、ライティング、動画編集など、フリーランス職種の生産性が大幅に向上しています。
「会社の看板がなくても、個人で稼げる時代が来た」という実感が、多くの人にフリーランス転身への意欲をもたらしています。
「フリーランスの不安より、会社の将来のほうが怖い」という声
多くの会社員がフリーランスに対して抱く不安には、「収入が不安定」「仕事が見つかるか不安」「孤独になりそう」といったものがあります。
しかし近年では、こうした不安よりも「今の会社に居続けるリスク」を感じる人が増えているのが実情です。
実際、終身雇用の崩壊、成果主義の導入、リストラの加速など、「会社にいれば安泰」という神話は過去のものとなりつつあります。
そのため、「不安があるからこそ、早めに準備してフリーランスとしても通用する力を身につけたい」と考える人が増えているのです。
また、X(旧Twitter)やYouTubeなどのSNSで、実際に会社員からフリーランスに転身した人たちの「リアルな声」が可視化されたことも影響しています。
現実的な体験談に触れることで、「自分にもできそう」と感じる人が後を絶ちません。
【チェックリスト付き】あなたはフリーランスに向いている?向かない?

自己判断の第一歩:「向いているか不安」は誰もが感じること
「自分はフリーランスに向いているのか?」という疑問は、誰しもが一度は抱くものです。
特に会社員から独立を考えている人にとって、向き不向きの判断は非常に重要なポイントです。
ただし、最初から完璧に「向いている人」など存在しません。
多くの人は不安を抱えながらも、少しずつ経験を積み、自分のスタイルを築いていくものです。
そのため、この章では「向いている人」「向かない人」の特徴を比較しながら、自己判断の材料を提供します。
自分に合っているかを客観的に見つめることで、準備の方向性も明確になります。
【チェックリスト】フリーランスに向いている人の特徴10項目
以下のリストに多く該当するほど、あなたはフリーランスに向いている可能性が高いと言えます。
- 自分のペースで仕事をしたいと思う
- 会社の組織や人間関係にストレスを感じやすい
- 自己管理能力があるほうだ
- スキルや知識を自分で磨くのが好き
- 新しいことに挑戦するのが苦にならない
- 目標を立てて、それに向かって行動するのが得意
- 1人でもコツコツ作業を続けられる
- 収入が不安定でもある程度耐えられる
- 発信活動(SNS・ブログなど)に抵抗がない
- 会社に依存せず生きていきたいと考えている
6つ以上当てはまった場合は、かなり適性があるといえるでしょう。
逆に、該当が少なかった場合は、まず副業などから始めて向き合っていくのがおすすめです。
逆に「フリーランスに向かない人」の典型例と対策
フリーランスに向かないとされるタイプも、いくつかの傾向に分類されます。
しかし、それらは必ずしも「向いていない=なれない」ではありません。
課題を理解し、対策を講じれば十分にカバー可能です。 【向かない傾向とその対処法】
- 自己管理が苦手
→ タスク管理ツールを活用して習慣化 - 孤独に弱い
→ コワーキングスペースやオンラインコミュニティに参加 - 営業・交渉が苦手
→ マッチングサービスを使って実績作りからスタート - 収入の波に不安が強い
→ 固定契約やサブスクリプション型の仕事を優先的に確保 - 生活の変化にストレスを感じやすい
→ まず副業で段階的に慣れる
要するに、自分の「弱み」を認識したうえで、準備や工夫を重ねることが重要です。
多くのフリーランスは、不安や欠点を補いながら成長していきます。
向いている/向かないの軸は「価値観」にある
フリーランスへの向き不向きは、スキルや性格だけでは判断しきれません。
もっとも重要なのは「働くことに対する価値観」です。
例えば、「自分の時間を自由に使いたい」「好きなことを仕事にしたい」「成果で評価されたい」といった価値観が強ければ、フリーランスのほうが満足度が高くなる可能性があります。
一方、「安定が第一」「仕事はルールに従ってこなすもの」「責任はチームで分担したい」という価値観が強い場合は、会社員のほうが合っているかもしれません。
価値観は良し悪しではなく、選び方の基準です。
自分にとって何を優先したいかを見極めることで、納得のいく選択ができるようになります。
会社員時代にやるべき「5つの準備」具体的ステップ解説

① スキルと実績を可視化する:あなたの「商品価値」を作る
フリーランスとして仕事を得るためには、まず「どんなスキルを持っていて、どんな成果を出せるのか」を明確にする必要があります。
スキルや知識があっても、それが相手に伝わらなければ仕事にはつながりません。
会社員時代のうちにやっておきたいのは、自分の経験を「実績」として整理し、プロフィールやポートフォリオにまとめておくことです。
たとえば、営業職であれば「年間売上◯◯万円を達成」、デザイナーなら「制作物の掲載媒体・反応数」など、成果が数字や実物で示せる形が理想です。
ポートフォリオはNotionやGoogleスライドなど無料ツールで作成可能です。
また、ブログやSNSでアウトプットしていくことで、「この人に頼みたい」と思われるブランド力を築いていけます。
② 安定した収入源の確保:副業で案件を受けてみる
会社員のうちに副業を始め、少なくとも月に3万円以上の収入が継続して得られる状態を目指しましょう。
これは、「需要があるスキルを持っているか」「自分が継続的にこなせるか」を見極める大切なステップです。
まずはクラウドソーシング(例:クラウドワークス、ランサーズ)やスキル販売サイト(ココナラ、SKIMA)を活用して、小さな案件から始めましょう。
SNSを通じて案件を受注する人も増えています。 継続的な収入が生まれれば、退職後の精神的・経済的な不安が格段に減ります。
また、実際のクライアント対応を経験することで、業務フローや時間配分、自分の得意不得意も把握できます。
会社員の給料という「安全網」があるうちに、できるだけ試しておくことが成功率を高める鍵です。
③ 人脈と発信:1人でも仕事が舞い込む「仕組みづくり」
フリーランスにとって、人とのつながりが「次の仕事」につながる最大の資産になります。
特に最初のうちは、過去の知人・同僚・SNSフォロワーなど、すでに信頼関係のある人たちから案件を紹介されるケースが多くあります。
そのためには、今のうちから人とのつながりを大切にし、「自分が何者か」「何ができるか」を定期的に発信しておくことが重要です。
X(旧Twitter)やInstagram、note、ブログなど、あなたのキャラや分野に合ったメディアで構いません。
「〇〇の案件あれば声かけてください」と発信するだけでも十分です。
また、オンラインサロンやコミュニティに参加することで、リアルな相談やコラボの機会も増えていきます。
人との接点は未来の仕事への種まきです。
意識してコツコツ育てていくことが、独立後の安定を支えます。
④ 保険・税金・制度の知識:お金周りの「落とし穴」を回避
会社員の間は、税金や保険など多くの手続きが会社に任されています。
しかし、フリーランスになるとこれらすべてを「自分で管理・手続き」する必要があります。
最低限、以下の項目について理解しておくと安心です。
- 開業届の提出方法とタイミング(税務署)
- 青色申告のメリットと帳簿のつけ方
- 国民健康保険・国民年金の手続き
- 事業経費の考え方とレシートの管理
- 住民税・所得税の納付タイミング
また、扶養や配偶者控除、家族の保険など、家庭に関わるお金の影響もチェックが必要です。
不明点が多ければ、税理士に相談したり、市区町村の無料相談窓口を活用しましょう。
知らなかったがために損をしたり、後であわてて処理しなければならない事態を防ぐことができます。
⑤ 生活費の見直しと資金計画:準備期間は「3ヶ月分の貯金」が目安
フリーランスに転身した直後は、収入が不安定になることも珍しくありません。
そのため、生活防衛資金として、最低でも3ヶ月分の生活費を貯金しておくことを強くおすすめします。
具体的には、以下のような支出を把握し、削減できる項目は早めに調整しておきましょう。
- 固定費(家賃・光熱費・通信費)
- 変動費(食費・交際費・趣味)
- 事業経費(ソフト・サブスク・ツール)
- 突発費(医療・税金・修繕など)
さらに、フリーランスとしての初年度は「売上があってもすぐに使わない」マインドが大切です。
経費・税金・翌月の売上未定分を差し引いたうえで、余裕ある生活設計をする意識を持ちましょう。
準備不足=不安の原因になりやすいため、資金計画は独立準備の要です。
退職前に絶対にやっておくべき「見落としがちなこと」まとめ
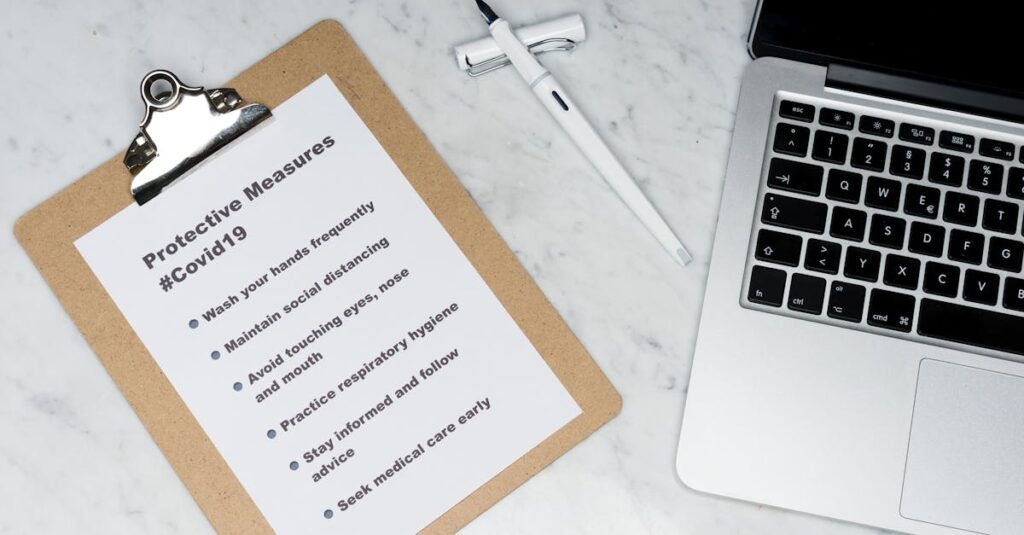
クレジットカード・ローンの審査は「会社員のうち」に済ませる
フリーランスになると、信用情報の審査が一気に厳しくなるのをご存じでしょうか?
なぜなら、企業に勤める会社員は「安定した収入源がある」と見なされる一方で、フリーランスは「収入が不安定」と見なされるためです。
そのため、以下のような手続きは退職前=会社員の身分のうちに済ませておくのが鉄則です。
- クレジットカードの新規発行・限度額アップ
- 住宅ローン・自動車ローンの申し込み
- スマホ端末の分割購入・Wi-Fi契約
- 賃貸契約の更新・引越し手続き
特にクレジットカードは、独立後に作ろうとしても審査に落ちることが多く、事業用カードすら作れないケースも。
今後のビジネス支出や生活資金のやりくりを考えたとき、信用力があるうちに「必要な枠」を確保しておくことがリスク回避になります。
健康保険と年金の切り替え手続きは「退職日から14日以内」
会社を辞めると、厚生年金と健康保険は自動的に喪失し、国民年金・国民健康保険へ切り替える手続きが必要になります。
この手続きは、退職後14日以内に市区町村の窓口で行う必要があり、遅れると延滞金が発生することもあります。
また、以下のような選択肢もあるため、どれを選ぶのがベストか事前に調べておくことが大切です。
- 国民健康保険に加入する
- 健康保険の任意継続を選ぶ(2年間可能)
- 配偶者の扶養に入る(条件あり)
特に任意継続は、退職後20日以内という締切があるため、保険証の返却・新規取得のタイミングを綿密に調整しましょう。
年金も同様で、切り替えを怠ると将来的な受給額に影響します。
社会保険は複雑ですが、役所や年金事務所での相談を積極的に活用するとスムーズです。
失業保険は原則「自己都合退職のフリーランス」には適用されない
フリーランスになるために自己都合で退職する場合、多くの人が「失業保険は受け取れない」と誤解しています。
実際には、以下のような条件下では原則受給できません。
- 自己都合退職で、再就職の意思がない
- 開業準備・副業などを行っている
- ハローワークへの積極的な求職活動がない
ただし、「一時的に失業保険を活用してから、のちに開業する」という選択肢も存在します。
この場合、給付制限期間中に開業届を出してはいけないなど、非常に慎重なスケジューリングが求められます。
また、扶養家族がいる場合の保険・年金の影響や、アルバイトでの収入との兼ね合いなど、知らないと損をする知識も多くあります。
「もらえるはずの失業給付を無駄にした」という声もよく聞かれるので、ハローワークで事前に相談しておくのが安心です。
引継ぎ・退職交渉は「感情」ではなく「戦略」で行う
フリーランスを目指して退職することは、個人の自由です。
しかし、その伝え方・タイミングによって、あなたの「独立後の信用」にも大きな影響を及ぼすことがあります。
たとえば、感情的に「もう辞めます!」といった退職は、職場に不信感を与えるばかりか、今後の人脈・紹介案件・業界内の評判にもマイナスです。
理想的なのは、以下の流れを意識した「戦略的な退職」です。
- 退職の2~3ヶ月前には上司に相談
- 業務引継ぎ用の資料を作成する
- 同僚・部下への感謝の言葉を忘れない
- 円満退社の雰囲気を演出する
特に、元同僚や上司が、独立後の「顧客」や「案件紹介者」になるケースは非常に多くあります。
最後の印象が良ければ、後々の収入に直結する可能性もあるのです。
「辞め方」は、フリーランス人生の土台を作る第一歩だと考えて丁寧に行いましょう。
不安との向き合い方:会社員からフリーランスへの「メンタル準備」

フリーランスになることの「不安」は正常な反応である
会社員からフリーランスになるという決断には、多くの人が不安を感じます。
これはごく自然な感情であり、決して「自分だけが怖がっている」わけではありません。
なぜ不安になるのか? 主な理由は以下のとおりです。
- 収入が安定しないのでは?
- 仕事が取れなかったらどうしよう
- 孤独になりそう
- 社会的信用が下がるのでは?
- 将来設計ができなくなるのでは?
これらの不安は、実際に独立した人たちも最初は皆が感じていたことです。
しかし、不安があるからこそ、準備を重ねて対策し、成長していく機会にもなります。
「不安=失敗」ではなく、「不安=慎重になれる力」だと捉えることで、前向きな行動につなげていけます。
「不安に強い人」ではなく「不安と付き合える人」を目指す
フリーランスに向いている人は、必ずしも「不安を感じない人」ではありません。
むしろ、不安を感じながらも、淡々とやるべきことをやり続けられる人こそが、継続的に成果を出せるのです。
そのために大切なのは、以下のような「不安との付き合い方」を身につけることです。
- 小さな成功体験を積み重ねて「自信の土台」を作る
- 失敗しても復活できる「選択肢(副業・アルバイト)」を確保しておく
- 定期的に話せる仲間・メンターとつながる
- 収入やスケジュールを「見える化」して予測できる安心感を作る
「全部を完璧に準備してから動く」のではなく、「動きながら不安と共存する」姿勢が、最終的な安定につながります。
不安を感じる自分を責めず、「不安を前提とした戦略」を持つことが、フリーランスとして長く続けるカギです。
リアルなフリーランスの1日:理想と現実のギャップを知る
フリーランスに憧れる理由として、「自由そう」「好きなことだけできそう」という印象があります。
しかし、実際のフリーランスの1日は、意外にも会社員以上に地道で自己管理が問われるものです。
たとえば、あるWebライターの1日のスケジュールは以下の通りです。
8:00 起床・家事 9:00 メールチェック・タスク整理 10:00 記事執筆1本目(2時間) 12:00 昼食・仮眠 13:30 記事執筆2本目(2.5時間) 16:00 クライアントMTG・案件対応 18:00 夕食・入浴・休憩 20:00 SNS投稿・ブログ更新 22:00 明日の準備・就寝
このように、「自由だけど、自律が求められる生活」がフリーランスの日常です。
時間に縛られない代わりに、成果を出すには自己コントロールが不可欠になります。
理想だけを追い求めると、現実とのギャップに苦しむことがあります。
現実のライフスタイルを想像しながら準備を進めることが、不安を減らす一歩になります。
支え合える仲間・コミュニティの存在が「孤独」を和らげる
フリーランスとして働く上で、多くの人が抱えるもう一つの大きな不安が「孤独」です。
上司も同僚もいない環境は自由である反面、相談できる相手がいないことで判断を誤ったり、精神的に消耗してしまうリスクもあります。
そこで重要になるのが、共通の悩みや情報を共有できる仲間やコミュニティの存在です。
オンラインサロン、X(旧Twitter)でのゆるいつながり、仕事系のチャットグループなど、目的に応じたコミュニティに所属するだけでも安心感が違います。
ポイントは、「完璧な相談相手」ではなく「気軽に話せる人」を何人か持つこと。 月に1回だけでも雑談できる相手がいれば、孤独感や焦燥感は大きく軽減されます。
フリーランスは一人のようで一人ではありません。
意識的に人との関係性をつくることで、長く健康的に続けていくことができます。
===
英語を身に付けて活かしたいなら、こちらの記事もご覧ください。