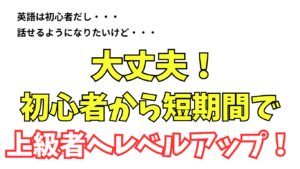副業と転職、両立できないのはなぜ?実例から学ぶ成功パターン

転職したのに副業まで無理…という声が増えている理由
働き方改革と副業解禁ブームの影響
近年、政府の働き方改革の推進により、多くの企業が副業を容認するようになりました。
これにより「副業=自由で賢い働き方」というイメージが急速に広まり、転職後に副業を始める人が増加しています。
特にSNSやビジネス系インフルエンサーの発信では、「会社に頼らない生き方」や「収入源の複数化」が強調され、あたかも誰でも簡単に両立できるような印象を与えています。
しかし、実際には転職後というのは新しい職場環境や人間関係、業務内容に慣れるために大きなエネルギーを必要とします。
そんな中で副業まで一気に始めてしまうと、体力的にも精神的にも消耗しやすくなり、思うように進まないことが多いのです。
また、企業側は「副業を許可する=業務に影響して当然」という雰囲気を出してしまうケースもあり、従業員に無言のプレッシャーを与えることも。
結果、「副業をやらなければ生活は苦しいまま」「やれば会社から睨まれかねない」という空気が、焦りを生んでしまっています。
このように、制度と現実のギャップが、転職後に副業で失敗・挫折する人を増やす要因になっているのです。
転職直後の“適応疲れ”が副業に追い打ち
転職は人生の一大イベントです。
新しい職場での業務習得、社内文化への適応、人間関係の構築など、目に見えないストレスが山ほどあります。
この「適応疲れ」は、多くの場合、本人も気づかないうちに蓄積していきます。
特に真面目な人ほど「早く成果を出したい」「職場に溶け込みたい」と無理をしてしまい、帰宅後や休日にまで精神が休まらないという状況に陥ります。
そこへ副業が加わると、完全にオーバーワークになります。
頭では「副業もやらなきゃ」と思っていても、体と心がついてこない。
結果として、手が止まり、「自分には向いていない」と感じてしまうのです。
また、転職後は生活リズム自体が不安定になることが多く、これも副業の継続を難しくする一因です。
通勤時間が増えたり、始業・終業時間が変わったりすることで、以前と同じように副業に時間を割けないケースもあります。
つまり、転職直後に副業がうまくいかないのは、ごく自然なこと。
決して意志や能力の問題ではなく、単に「回復と適応の時間が必要」なだけなのです。
SNSに踊らされる“副業成功の幻想”
InstagramやX(旧Twitter)、YouTubeなどでは、「転職して収入アップ」「副業で月10万」「自由な働き方が実現できた」といった華やかな投稿があふれています。
これらの発信は確かに魅力的ですが、多くの場合“ごく一部の成功例”を切り取ったものです。
努力や試行錯誤の過程を省き、成果だけを見せる構成がほとんどで、それを見た人は「自分もすぐに稼げるはず」と錯覚してしまいます。
しかし現実は、ほとんどの人が副業で成果を出すまでに数ヶ月〜数年かかるのが当たり前。
しかも、転職直後という慣れない時期に始める場合、成功確率はさらに下がります。
SNSで見かける成功談の裏には、何度もの失敗や諦めた副業があるかもしれません。
そうした「見えない部分」が省略されているために、現実と理想のギャップに苦しむ人が後を絶たないのです。
副業の情報収集にSNSを使うのは悪いことではありませんが、それが「比較」や「焦り」につながるようなら、一度距離を置くことも必要です。
実際の相談事例:副業を始めたが続かず挫折した20代男性
都内でIT企業に転職したAさん(28歳)は、前職では副業禁止だったため、転職を機にWebライティングの副業をスタートしました。
ところが実際に取り組んでみると、思った以上に「時間が取れない」「やる気が湧かない」という現実に直面したといいます。
Aさんの本業は残業が比較的少ない職場でしたが、転職してまだ3ヶ月しか経っておらず、業務に対する理解や社内コミュニケーションに気を使う日々。
帰宅後にはぐったりしてしまい、副業に手をつける余裕がありませんでした。
「ライター案件も提案し続けないと仕事が来ないし、書くのにも意外と時間がかかる。最初は楽しかったけど、どんどん義務になっていって苦しかった」と話します。
最終的にAさんは、副業を一旦ストップすることにしました。
代わりに、通勤中にKindleで文章力やマーケティングの本を読むなど、インプット中心の時間に切り替えたのです。
「今はあえて“準備期間”として考えている。次に余裕ができたときに再挑戦したい」と前向きに語ってくれました。
このように、「一度やってみたけどうまくいかなかった」という実例は非常に多く、それ自体が失敗ではなく“学び”や“調整”としてとらえることが大切です。
転職と副業、両立できないのは「普通」です

人間には回復時間が必要
現代社会では「効率化」「生産性向上」「スキマ時間の活用」といった言葉が当たり前のように飛び交っています。
その影響で、常に何かをしていないと不安になる人も少なくありません。
しかし、私たち人間は機械ではありません。
体力も精神力も無限ではなく、特に環境が大きく変化したときには“回復時間”が必要になります。
転職というのは、まさにそのような変化のひとつ。
仕事内容だけでなく、人間関係、会社の文化、通勤ルートまで変わることで、心身ともに負担がかかるのです。
副業は本来自由度の高い取り組みであり、義務ではありません。
しかし多くの人が「副業もやらなければ」「空いてる時間に何かしなきゃ」と焦ってしまい、自分を追い込んでしまいます。
その結果、疲れが抜けない・モチベーションが上がらない・効率が悪くなるといった悪循環に陥ることも。
これは本人の努力不足ではなく、単純に“人間らしい反応”なのです。
「今日は疲れたから副業は休もう」「回復に専念する時期だ」と認識することこそ、長く働き続けるための戦略です。
副業をやめることではなく、“一時停止”する勇気が、人生全体のバランスを整える第一歩になります。
両立できないのは意志や努力の問題ではない
多くの人が「自分には副業を両立できるだけの意志が足りない」「頑張りが足りないのでは」と自責的に考えてしまいます。
しかし、実際は意思や努力とは無関係な要素が大きく影響しています。
たとえば、通勤時間が片道1時間を超える人や、家庭の事情で夜の時間が取りづらい人、あるいは職場でのストレスが強い環境にいる人にとって、毎日副業に時間を割くのは現実的ではありません。
さらに、業務内容のハードさも関係します。
肉体労働や神経を使う仕事をしている場合、帰宅後に「何かを学ぶ」「作業をする」という余力が残っていないのは当然のことです。
つまり、「副業が続かない=ダメ人間」ではなく、「環境が整っていない=当然の結果」なのです。
これは運やタイミングの問題でもあり、自分を責める必要はまったくありません。
逆に言えば、自分の現状を正しく認識し、環境が整うまで無理をしないことが、長期的にはもっとも効率の良い選択になります。
意志や根性に頼らず、現実的な視点で判断することが大切です。
まずは“両立ありき”の思考を捨てよう
「副業もやらなければ」「本業と両立しなきゃ」といった思考に縛られていませんか?
この“両立前提”の考え方が、あなたを苦しめている可能性があります。
副業は義務ではなく、自分の生活や人生に合ったタイミングで取り組むものです。
にもかかわらず、SNSや世間の空気感に押されて「やらないと遅れている」「自分も何かやらなければ」と思ってしまいがちです。
ですが、副業には適した時期とそうでない時期があります。
転職直後やプライベートが忙しい時期に無理をしても、良い結果は生まれません。
むしろ焦りから中途半端に取り組んで失敗し、自己肯定感を下げてしまうリスクがあります。
まずは「今は両立しなくてもいい」「必要な時が来たら始めよう」という柔軟な思考に切り替えましょう。
その方が結果的に長く、副業を続けられる可能性が高まります。
“やるかやらないか”の二択ではなく、“今は充電中”という選択肢を持つこと。
それが、現代の働き方においては非常に賢い判断なのです。
共感を呼ぶ実例紹介:30代女性が感じた「しんどさ」と気づき
Bさん(33歳・女性)は、広告代理店からベンチャー企業へ転職しました。
転職理由は「裁量ある働き方」と「副業解禁」でした。
入社後すぐにオンライン講師の副業を始めたものの、1ヶ月で続けられなくなったといいます。
「新しい仕事に慣れるのに精一杯で、副業の準備が全然進まなかったんです。毎日疲れ果てて、夜や週末にパソコンを開くのも億劫になってしまいました」
彼女は当初、「自分には根性が足りないのかも」と悩みました。
しかし、同じような境遇の友人たちの話を聞くうちに、「むしろできていない人のほうが多い」と気づき、気持ちが軽くなったそうです。
「副業って、SNSではキラキラして見えるけど、実際はすごく地味で地道な作業ばかり。しかも、本業が慣れないうちは、そんな余裕ないのが普通なんだって思えるようになってから、心がラクになりました」
今では副業を一旦休止し、週末は読書や友人とのカフェ巡りなど、リフレッシュの時間を大切にしています。
「もう少し落ち着いたら、またチャレンジしたい」と、前向きな気持ちを取り戻しました。
このように、自分を責めるのではなく「これが普通」と認めることで、気持ちが大きく楽になるケースは非常に多いのです。
両立できないあなたが見直すべき4つのポイント

本業の慣れに時間をかけるのは悪いことではない
転職直後というのは、想像以上に多くのエネルギーを必要とする時期です。
新しい業務フローを覚え、同僚との関係性を築き、企業文化に馴染むには、少なくとも数ヶ月はかかるのが普通です。
しかし、多くの人が「早く結果を出さなければ」「すぐに副業もこなさなければ」と焦ってしまい、自分自身に過剰なプレッシャーをかけてしまいます。
その結果、本業でミスが増えたり、精神的に追い詰められたりすることもあります。
ここで重要なのは、「本業に集中する期間があって当然だ」という認識を持つことです。
副業を後回しにすることは、“逃げ”ではなく“戦略”です。
むしろ本業にしっかりと慣れてから副業を始めるほうが、結果的にスムーズに両立できるようになります。
「最初の3ヶ月は本業のみに集中する」「副業は土日だけの軽いものから始める」といったステップを踏むことで、精神的な負担も軽減されます。
自分のペースで慣れていくことを許す。
それは決して“怠け”ではなく、長期的なキャリアにおいて極めて賢明な判断なのです。
副業は“挑戦”ではなく“余裕”の中でやるべき
副業を始めるとき、多くの人が「自分を変えたい」「もっと成長したい」といった“挑戦”の気持ちで取り組みます。
もちろん意欲は素晴らしいことですが、タイミングを誤ると自分を苦しめる原因になってしまいます。
副業は本来、“余裕の中で取り組むもの”です。
時間的にも、精神的にも、ある程度の余白がないと継続は難しくなります。
転職直後や、生活が不安定な時期に「自分を追い込む手段」として副業を始めると、結果的にストレスや挫折を招くことになります。
たとえば、残業が多い仕事をしている人が、平日夜に副業を詰め込もうとすると、睡眠不足や疲労が蓄積し、どちらの仕事も中途半端になりがちです。
そうなると「自分は能力がない」と誤解してしまうことも。
まずは「今日は時間があるから副業に手をつけよう」「今月は忙しいから一旦お休みしよう」というように、自分のペースを尊重することが大切です。
“頑張ること”と“無理をすること”は違います。
副業は、やる気に満ちているときだけでなく、余裕があるときにこそ、良い成果を出せる活動です。
収入目的の副業は最初はむしろコスパが悪い
副業を始める大きな理由のひとつが「収入を増やしたい」という目的です。
しかし、実際にやってみると、多くの副業が最初は“時間と労力の割に報われない”という現実に直面します。
たとえば、ライティング、副業ブログ、動画編集など、人気のある副業であっても、実際に稼げるようになるまでには学習・練習・営業といった段階を踏む必要があります。
最初の数ヶ月は、時給換算すると数百円以下ということも珍しくありません。
そのため、「すぐに稼げるはず」と期待して始めると、現実とのギャップに落胆しやすく、継続が困難になります。
副業で収入を得るには、まず“時間投資”が必要です。
これは本業とは異なる性質であり、「収入=労働時間×時給」という単純な計算では測れません。最初は“勉強期間”や“試運転期間”と割り切り、少しずつ経験を積んでいく姿勢が重要です。
そのうえで、自分に合ったスタイルやスキルが身についてから、本格的に収益化を目指すのが理想です。
副業で焦って稼ごうとするより、じっくりと「長く続けられる形」を築くことが、結果として最も効率的な方法になります。
「できない自分を責めない」マインドの整え方
副業がうまく続かないとき、多くの人は「自分には向いてないのかも」「やっぱり能力がない」とネガティブな感情に陥りがちです。
しかし実際には、そう感じること自体がごく自然な反応であり、恥ずかしいことではありません。
むしろ、自分を責め続けることの方が、精神的な消耗につながります。
そこで必要なのは、「できないこともある自分」を受け入れ、優しく扱うことです。
たとえば、「今日は疲れたから何もしない」「副業を一時休止して、趣味の時間を大切にする」といった行動は、決して甘えではありません。
むしろ、自分のバランスを保つために必要なセルフケアなのです。
また、「できなかった」ことではなく「できたこと」に意識を向ける習慣も効果的です。
本業で新しい業務を覚えられた、定時で帰れた、よく眠れた。それだけでも十分に価値があります。
副業は人生をより良くするための“手段”であって、自分を苦しめる“義務”ではありません。
自分に対して厳しすぎず、温かく見守るマインドを持つこと。
それが、結果的に継続力や成果につながっていくのです。
両立成功者に共通する“戦略的な”副業スタイルとは?
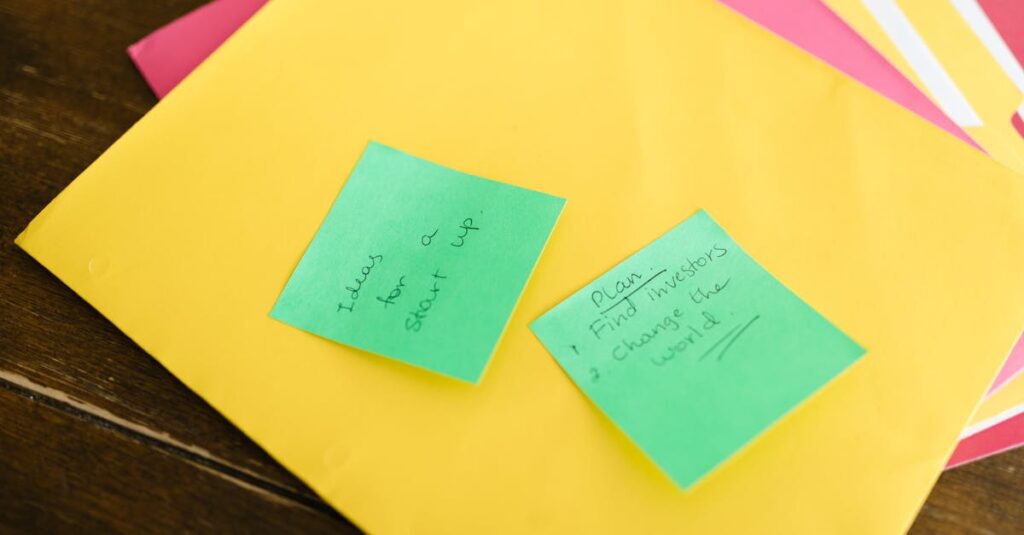
副業のジャンル選び(時間・体力・スキル)
副業で成功している人に共通しているのは、「自分に合ったジャンルを見極めている」という点です。
単に流行っている、儲かりそう、という理由ではなく、自分の時間、体力、そしてスキルに合うかどうかを冷静に判断しています。
たとえば、平日は残業が多く、帰宅後はヘトヘトという人が、集中力と長時間労働が求められる動画編集を選んでも、継続は難しくなります。
一方で、すきま時間にスマホでできるポイントサイトやタスク型のライティングであれば、負担は少なく済みます。
また、スキルとの相性も重要です。
人前で話すのが得意な人はオンライン講師やコーチングが向いていますし、文章を書くのが好きならブログやnoteが適しているかもしれません。
無理に自分を変えるのではなく、「今の自分で勝負できる領域」を選ぶことが、最初の成功につながります。
副業は“適正×継続性”が命。
ジャンル選びにおいて「楽しさ」「続けやすさ」「成長可能性」の3点でフィルタリングすることをおすすめします。
これにより、「最初は少しでも、気づけば成果が出ていた」という自然な成長が可能になります。
継続しやすい時間の取り方・習慣化
副業で成果を出すには、「継続」が何よりも大切です。
そのためには、「気合い」や「意志」だけでなく、日常生活に副業を“自然に組み込む”ことが求められます。
成功者は、一日のどこかに“固定枠”を作っています。
たとえば、毎朝出勤前の30分、寝る前の20分、土曜の午前中など、無理のない範囲でスケジュールに組み込むことで、副業が“生活の一部”になっているのです。
また、「トリガー習慣」と呼ばれる手法も有効です。
たとえば、「コーヒーを飲んだら副業開始」「YouTubeを1本見たら記事作成に着手」など、特定の行動と副業を結びつけることで、自然と作業に入れるようになります。
重要なのは、「完璧を求めすぎないこと」。
1日1時間と決めても、疲れている日には10分でもOK。
とにかく“毎日ちょっとずつ触れる”ということが、モチベーションと成果の両立につながります。
継続とは、気分任せでやるものではなく、“仕組み化された習慣”であるという認識が、副業成功の鍵なのです。
モチベーションではなく“仕組み”で回す
副業に取り組む多くの人が陥るのが、「モチベーション頼り」の罠です。
「やる気が出た日だけ作業を進める」というスタイルは、最初は良くても長続きしません。
むしろ、気分の波に左右されて作業が停滞する原因となります。
両立に成功している人たちは、このモチベーションという不安定な要素に依存しない“仕組み”を構築しています。
たとえば、作業ルーチンを定めて自動化したり、タスクを細かく分けて「やることが明確な状態」を作ったりすることで、迷わずに取りかかれる環境を整えています。
また、「他人との約束」を活用するのも有効です。
クライアントとの納期や、仲間と一緒に進めるプロジェクトなど、第三者の目があることで強制力が生まれます。
さらに、成果を可視化することで自分自身を鼓舞する方法もあります。
「月に〇件納品」「週に〇記事作成」といった数値目標を設定し、達成を記録していくことで、自信と継続意欲が生まれます。
モチベーションは一時的な熱量に過ぎませんが、仕組みはあなたを長期的に支える“エンジン”となります。
成功者が無理なく副業を続けられるのは、この“仕組み化”が徹底されているからなのです。
実例紹介:本業×副業を無理なく回す40代のケース
Cさん(42歳・男性)は、中堅メーカーの営業職として働きながら、副業でオンライン販売を行っています。
平日は朝8時に出勤し、帰宅は夜7時。
決して時間に余裕があるわけではありませんが、無理なく副業を続けて3年になります。
その秘訣は「徹底した仕組み化と自動化」です。
Cさんは副業で、特定ジャンルの商品を仕入れてネット販売していますが、仕入れのタイミングは毎週土曜の午前中と決めており、発送作業は平日夜の1日だけに集約しています。
さらに、在庫管理や顧客対応の一部は外注化しており、自分が関わるのは最小限。
「仕事が忙しくても、副業の作業量が読めるから安心感がある」と語っています。
また、Cさんは毎月の収支や作業時間を記録しており、無理のない範囲で収益を最大化する工夫をしています。
「副業は“やるぞ!”という気持ちより、“どうやって効率化するか”のほうが大事」と言い切る姿勢が印象的です。
彼のように、「生活の中に副業をどう組み込むか」「どこを省力化するか」という視点を持つことで、年齢やライフスタイルに関係なく、副業を成功させることが可能になるのです。
両立にこだわらない、新しい働き方の提案

転職直後は「副業しない」という戦略も正解
副業が注目される時代だからこそ、あえて「副業をしない」という選択肢も有効です。
特に転職直後のタイミングは、環境の変化に対応するだけで大きな負荷がかかるため、無理に副業まで抱えるとオーバーワークになりかねません。
ここで重要なのは、「今は準備期間」と割り切ること。
たとえば、新しい業務に集中しながら、スキルを蓄積したり、将来的に副業につながるテーマを見つけたりする時間にあてる方が、長い目で見て効果的です。
また、何もしないわけではなく、「副業に向けた下地作り」をするという戦略もあります。
副業関連の本を読んだり、興味のある分野の情報を集めたり、小さなアウトプット(SNS投稿やメモなど)を続けることで、スムーズな再スタートが可能になります。
周囲に「副業をやっていない自分は遅れているのでは」と感じる人もいるかもしれませんが、それは思い込みにすぎません。
本業に適応してからでも十分間に合いますし、その方が結果的に効率よく動けます。
「何もしない」ことが、実はもっとも戦略的な“準備”になることもあるのです。
本業内で副業的スキルを身につける道もある
副業は何も社外でお金を稼ぐことだけを意味するわけではありません。
実は、本業の中でも“副業的スキル”を伸ばすことができるケースは多々あります。
たとえば、資料作成やプレゼンの機会がある場合、そこで培ったデザイン力や伝達力は、のちにライティングやYouTubeのスクリプト制作などに応用できます。
経理や数字管理に強くなれば、フリーランスの確定申告や資産運用にも役立ちます。
また、社内の教育担当を任された経験が、将来的にオンライン講師やコンサル業に繋がることもあります。
このように、本業の中で“市場価値のあるスキル”を育てておくことで、副業を始めるときに有利なスタートを切ることができます。
この視点を持つと、本業に対してもモチベーションが上がりやすくなります。
単なる“仕事”ではなく、“将来への投資”と捉えられるようになるからです。
無理に社外活動をしなくても、本業の中で「副業力」を養うことは十分に可能。
むしろ、地盤が固まってから外に広げていく方が、継続性・収益性ともに高まる傾向にあります。
フリーランスや業務委託との違いと可能性
副業を続けていく中で、「いっそフリーランスになった方が良いのでは?」と考える人も少なくありません。
しかし、フリーランスや業務委託と副業との間には、明確な違いがあります。
副業は“本業に影響を出さない範囲での活動”であり、収入や責任も比較的小規模です。
一方で、フリーランスや業務委託は、“自己完結の働き方”であり、仕事の受注・納品・経理・営業などすべてを自分で行う必要があります。
この自由度の高さは魅力的ですが、同時に「自分で全責任を負う」リスクも伴います。
安定収入が保証されていないため、生活が不安定になる可能性もあるのです。
ただし、現在は“複業”という中間的な選択肢も注目されています。
たとえば、本業を週3日に抑えて、残りの時間を業務委託や個人活動にあてるという働き方です。
これにより、安定と自由のバランスを取りながら、自分の可能性を広げることができます。
副業にこだわらず、「どう働きたいか」「どんなライフスタイルを送りたいか」という視点で、自分に合った形を模索することが、今後ますます重要になっていくでしょう。
無理せず収入を増やす選択肢は意外と多い
副業をしなくても、収入を増やす方法は意外と多く存在します。
たとえば、固定費の見直し、副業的な収入源の自動化、本業での昇進・資格取得など、すでに持っているリソースを活用することで得られるメリットは大きいです。
具体的には、以下のような手段が考えられます:
- 通勤定期や保険の見直しで毎月1万円以上の節約
- 投資信託の自動積立による資産形成
- ポイントサイトやキャッシュレス決済の活用で実質還元を得る
- 業務効率化で評価が上がり、昇給につながる
これらは副業のように「新たな時間やエネルギー」を投入しなくても、結果的に収入アップにつながる行動です。
また、「自分の得意なことをフリマアプリで販売する」「知識をnoteでシェアする」などのライトな取り組みも、立派な収益化の第一歩です。
「副業=大きなプロジェクト」「毎月〇万円稼がなければ意味がない」と考える必要はありません。
小さなアクションを積み重ねることで、気づけば収入が増えていた――そんな“無理のない戦略”こそが、長く安定して続けるためのカギなのです。
===